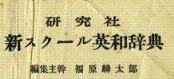8時半まで熟睡し、サン・マルコ広場でパキスタン学生と別れて、4つぐらい教会と美術館をみて回る。美術アカデミアが改装かなにかで半分しか開放しておらず、さしたる収穫なし。ただペサーロ宮のベネツィア・ビエンナーレ展の作品には共感をおぼえるものが多かった。
 暑くなってきたのでリド島の海水浴場に行って泳ぐ。浅い砂浜が続いて岩場がみあたらないのは残念である。水は澄んでいるとは言い難いが、波もなく穏やかでベニスに死すおそれはない。アサリを捕る。サン・マルコに戻って鐘楼より全市を一望し、日没をみる。
暑くなってきたのでリド島の海水浴場に行って泳ぐ。浅い砂浜が続いて岩場がみあたらないのは残念である。水は澄んでいるとは言い難いが、波もなく穏やかでベニスに死すおそれはない。アサリを捕る。サン・マルコに戻って鐘楼より全市を一望し、日没をみる。
ベネツィアには、他のどこの都市とも比較できない独特の風情がある。だいたい建物を出ると玄関正面の足元の階段を海水がピチャピチャ洗っているという光景は、それがどうして可能なのかと不思議がらせる。こんな所に、と思うような路地裏にまで運河が入り込んでいて、しかもそれが潮の干満と鯨が棲むという、あの海なのである。みはるかす水平線と大海原を、部分的とはいえ路地裏に押し込めて、こどもがオシッコをしているのは痛快である。
土曜日だからだろうか、夜中12時を過ぎても人々が河岸にテーブルと椅子をだしてワインを飲み、声高にさんざめき、子供が騒ぎ、犬が鳴いている。なかなか寝つかれなかったが「これがイタリアなのだ」とわりきる。


 今日は3つの美術館めぐりである。3日目にもなると道に迷うこともなくなる。最初のウフィッツィはエルミタージュ以来の混みようで、名のある美術館はやはり混みあうな。ボッティチェリの「春」と「ビーナスの誕生」に<
今日は3つの美術館めぐりである。3日目にもなると道に迷うこともなくなる。最初のウフィッツィはエルミタージュ以来の混みようで、名のある美術館はやはり混みあうな。ボッティチェリの「春」と「ビーナスの誕生」に<