『旅 行 記』 (1975年5月3日〜1976年3月20日)
1975年5月24日(土)
シリアン湖を巡る遊覧船は乗る人がいなくて開店休業、春は名のみの風の寒さや。
今日は50数キロ離れた県庁所在地ファルンに行って銅山博物館をみることにしたが、駅で待っていると、れっきとした国鉄本線に一両編成のワンマン・バスみたいな電車が入ってきた。乗ったのは私とあと1人、それでも速さは昨日の急行とかわらない。
ファルンは県庁所在地といっても1日16本の列車しかなく、土曜日で店も閉まっており、まるでゴースト・タウンのようだった。
世界でいちばん古いといわれるここの銅山の係員にしたがい、ヘルメットとコートを着用してエレベーターで坑道に降りる。土曜日の放課後、クラブをさぼって裏手の防空壕を探索した中学生時代を思い出す。廃坑の奥まったところで、機械化された現在の採掘状況の映画を観たが、吐く息も白く、立ったままでみる演出効果は充分だった。
帰りは時刻表の読み違えで乗換え駅で3時間もの待ちあわせとなり、長距離バスの便もなく、持参のソリテールというゲームを習熟することにする。これは32本のピンをジャンプして次々に取っていき、1本だけ残ればいいのだが、たいてい4、5本余ってしまう。研究して二度ばかり2本残すところまで成功したが、戦術的には各パートごとに確実に掃討していけばよいようだ。
帰途、夏至祭に使う気のはやいポールが立っているのをみる。タンポポはこの辺りまだ咲き揃ってなく、貧弱なツクシが生えている。肉料理にいれて食べてみたが、醤油のないのが悔やまれる。
今晩は合部屋に変更となったが、肥満体の中年がすでに高いびきで熟睡していた。このいびきがきわめて脅威的で、いい大人がこんなところにいるのも鼾のせいだろうと、彼の人生を追体験して気を紛らす。
1975年5月25日(日)
レクサンドからストックホルムに戻り、オスロにはいる日。ストックホルムからイエテボリまで行き、そこで乗り換えてオスロにはいる迂回コースをとるつもりで確認したところ、4時間あとの直通に乗れ、という。国鉄当局は時間通りに運行させる自信がなかったのだろう。そこで仕方なくオスロに遅れる旨電話をいれる。急行で6時間半の距離でも、隣国だから国際電話の扱いであった。
時間つなぎに地下道のベンチに坐って通行人をじっくり見ていると、ときおり民族衣装を着こなしたラップ系の人々が通り過ぎる。また犬を連れた人がとても多い。そのあと文化センターヘ行って、5日遅れのガーディアン紙で、統一教会の文鮮明の記事を読み、今日は日曜でとても混んでいたが、予約して「悲愴」を聴いた。今度は最後まで聴けた。
オスロ行き急行列車は定刻をしょっぱなから10分遅れて発車、良心的な国鉄マンの忠告どおりであるが、彼も情けなかったに違いない。
車内では60をすぎたアメリカの老人と一緒になり、いかにして最も能率的に北極圏に行って真夜中の太陽をみることができるかを、地図を広げ、時刻表を見、ウイスキーをちびちびやりながら研究し合う。
車窓から見る白夜の感覚は、夕方のそれよりも、陽が昇る前の、鳥もまだ啼き出さない夏の明け方の感じに近い。すなわち夕方の雑踏も日中の暖かさの淀みもない、静かな、ひんやりした明るさである。
夜11時タクシーでユースに駆けつける。
1975年5月26日(月)
旅行代理店に行って明日からのフィヨルド・ツァー3日間を申し込む。あとに退けない200ドルの大出費だが、フィヨルド自体よりも本格的なスモーガスボードを目一杯食べて、栄養を補給するのが目的である。
朝のうちに、誰もいないガランとしたオスロ国立美術館の一室で、E・ムンクと対峙した。3人の少女は、ながすぎる白夜の明るさに為す術も知らず橋上にたたずみ、倦怠と憂欝にさいなまされている。この美術館はムンクだけでもっているのかと思ったが、一巡すると近代の名画をずらり揃えた錚々たるものであった。
そのあと市庁舎前よりフェリーで対岸に渡り、両極を探検したフラム号と漂流船コン・チキ号をみる。10メートル近いイースター島の巨像をみたが、石膏造りの模像なのでがっくりする。
今日はすばらしく良い天気で、フログネル公園に日光浴の人を多くみた。ここの公園のビーゲランの手になる彫刻群には、天使像が1つもない。あるのは天使の乱舞と対をなす、清濁あわせ呑んだ人間の群像ばかりである。いたわりあう老夫婦のまわりを、羽根をつけて健康で快活な天使がほほえみながら祝福する、などという冗談は、一徹で真摯なビーゲランのよくするところではなかったのだろう。泣く姿は年経た人ほど冒しがたいと知る。
パチンコ屋みたいなビンゴ屋があったが、ノルウェー語で読み上げられているので参加をあきらめる。
夕食は、ユースを満員のため断られて野宿するという、日本人3人とオーストラリア人と一緒に芝生のうえでとる。部屋はスウェーデンの田舎から遠足に来た中1の少年たちと一緒になったので、さっそく折り紙を伝授する。「もっとキチンとやれ」と何度も言ったので、彼らは 「キチント」を覚え、面白い発音らしく、「キッチント、キッチント」と翌朝になっても連発していた。
1975年5月27日(火)
今日から3日間の豪勢なツァーに出る。料金が値上がりしており、しかも最近の交換レートのアップでたいへんな買い物となった。同乗の客はアメリカの中年夫婦がほとんどで、私もほどなくしがない教師とばれてしまう。
バスは湖とも河ともつかないフィヨルドを縫いながら、ノルウェーの内陸部をひた走る。麓にはテレビもない農家が散在している。わが国のように家庭的な暖かいだらしなさが屋外まで及んでいるというふうでなく、きちんきちんと独立した部署についているという感じである。
昼食は一室を占領する豪勢なスモーガスボードだったが、程度を越えればおいしくても飽きがくるのは道理である。
投宿したホテルの周辺は残雪多い冬景色で、凍結したティイン湖が眼下にあって寒々しい。
ユースにいると盗難や殺人(二件の目撃談を聞いた)や、ヒッチや野宿、食糧の買い込み、肉体労働、売血などの話をきく。金持ち相手のツァーに乗ると、未練気なく買い物をし、8ミリや写真を撮り、ガイドの小話に心から笑っている人々をみる。しかし彼らにしても永年お金を貯めて念願の外国旅行をしていることが、夫婦という単位から痛いほどわかる。
暖房のよく効いた部屋から一面氷に覆われた湖を望み、我が心は寒々としている。私の選んだ職場が最善であるのは、まぐれでなかったのかもしれないと思う。愛すべきものが他所にあって喜々としている。しかし私のいる所も捨てがたい。
<ブリダンのロバ> という例え話がある。飢えたロバがいて、左右等距離に餌が置いてある。ロバは等距離にあるのでどちらをとってよいか迷い、判断がつかずに餓死する、というものである。そこに意味を見いだすとすれば、振り返ってみて常に最善の道を選んできたか、という危惧を抱かせるのである。選ぶべきものの二つある時、ロバほどのかたくなさももたずに、安易に選んで最善であるかのごとく振るまい、心中他を悔やむような生き方を択らぬならば、此所に在ってしかも他に在ることのできぬ今、ロバのように身を固くして最も愚かしく生きるのが最善なのではないか、と考えられてくるのである。違う意味では、自分を捨てて常に最善のものを結び合わせようとする仲人のようなものである。趣味としては仲人は産婆よりも審美的だが、生き方としては産婆よりもいっそう惨めである。なぜなら仲人こそ<中間に在るもの(インテル・エッセ)>だからである。
愛すべきものが他所にあって喜々としている。しかし私のいる所も捨てがたい。
洟を垂らしてツギをあてた服の、さえない子供には、外国の名犬ラッシーの絵は尽きることのない憧れの的であり、芝生で跳び回るコリーの優雅さに、おそらく人間的な「気品」すら感じとっていたのだ。
例えば私はスキーに気押される気持ちがぬぐえない。あれほど颯爽とした世界にどうやって踏み込んでいけるのか。どうすればあの世界に仲間入りできるのか。級友の一人が3学期には雪焼けした顔で学校に帰ってくる。しかも宿題を済ませて、成績もよくて、友達からは好かれている。そこには私と別の世界、別のやり方があって、それは努力などというものでは追いつかない、もって生まれた「気品」というものがあったのではなかったか。学生時代、もっとも気楽な教会の仲間たちと白樺湖に行き、おどろおどろしいスキー器具を身につけ、ゲレンデを見やると、そこにいるのがいかにもふさわしく、いささかのぎこちなさもなく、しかもいることに謙遜し、はにかんでいる少年が、けれん味のないシュプールを描いて退屈気に降りていく。その瞬間、「食べていい?」「借りていい?」と乞い尋ねる時の自虐的な卑屈さが私を襲い、まっさらな雪さえが峻厳と人を区別してくるような錯覚に襲われたのだ。
私は今たいした用件もなく、コッツンヘイメン山塊にあるティイン湖のリゾート・ホテルにいる。ドレス・アップして晩餐に臨むも、中年夫婦との会話には辞令と気苦労ばかりで魅力がない。早々部屋に戻ってウィスキーを飲みながら、窓べにもたれて湖を凝視する。
1975年5月28日(水)
 バス旅行が続く。午後はフェリーに乗って世界最大といわれるソグネ・フィヨルドを見物するも、「なるほど」という程度である。今晩のホテルは渓谷を見下す位置にあって、歴代国王も投宿したことがあるといい、創立100年近い風格を誇っている。ウィスキーを飲んで早く寝る。
バス旅行が続く。午後はフェリーに乗って世界最大といわれるソグネ・フィヨルドを見物するも、「なるほど」という程度である。今晩のホテルは渓谷を見下す位置にあって、歴代国王も投宿したことがあるといい、創立100年近い風格を誇っている。ウィスキーを飲んで早く寝る。
1975年5月29日(木)
陽光ふりそそぐ中、粉風花が舞っている。
ガイドの実習生が3人乗っており、それぞれノルウェーの社会事業や歴史、スキーについて話す。「オラフ5世は今も国王である」というところを「yet
King 」 と言い、「still King だな」 と実習生同士小声で訂正している。
持ち金を計算すると7月中旬には切れてしまう勘定なので、予定より早く送金してもらうことにする。ガイドヘのチップをみんなで出しあうことになって、なけなしの10クローネ(800円)を取られて痛い。それでも音頭をとったオーストラリア人が、乗客一同として日本のジェントルマンを最初に挙げてくれて痛さを忘れる。
フィヨルドの水は微量の塩気をおびているが、圧倒的な雪解け水に海水が押されている。
バスは時々ノルウェー民謡を流し、ベルゲン近くになってその街が生んだ作曲家グリークの音楽を流していたが、重くて雰囲気にあわないためか、すぐに止めてしまった。
夕刻6時に別れを惜しんでみたりしてからバスを離れ、ベルゲン駅で寝台を予約して、ただちに水族館に向かう。道すがら氷雨がぱらつき、手がかじかみ、港街ベルゲンは非情であった。
水族館はヨーロッパ有数にしては魚類も施設も三保より劣っている。館内の照明を極端に暗くしていたのは趣向であったが、貝類や魚をみていると思い出してはならない寿司種がほうふつとしてくる。
そのあとはケーブルで小高い山に登ってベルゲン市街を見下す。ノルウェー第二の都市はこうも小さいのかと感嘆する。この海のむこうはアイスランドである。北西の方角から雨雲が垂れ込めてきたので急いで下山するも、雨でなく粉雪が舞い始めた。細い路地から港の岸壁を望み、濡れた舗道にたたずんで、思わず知らず「シェルプールの雨傘」を口ずさんでいる。
夜行で折り返しオスロに戻る。
1975年5月30日(金)
今日は移動日である。オスロからさらにストックホルムまで戻り、そこから北上して再びノルウェー国内のナルビクに入る。北極圏に入って真夜中の太陽をみるためである。地理的条件のせいだろうが、自国の都市に鉄道で入るために、いったん隣国まで出なければならないのは可笑しい。そのくせ通貨はノルウェー・クローネとスウェーデン・クローナが厳然としてあり、しかもきわめて似通っているので、あちらの首都こちらの首都と、こまごまスーパーで食糧を買い込む者にとっては煩わしい。
気軽に首都から首都へ、さらに国内有数の都市へと移動しているが、3日間のバス旅行を経てみると、やはり首都を首都たらしめている国力や、文化的歴史的風土的背景があって、首都を支えているそれら国土の隠然たる底力がその国の表玄関の体面を保たせているのだ、ということが分かる。
1975年5月31日(土)
朝になってオスロで知り合ったホステラーが車内に同乗していたのを知る。鉄鉱の街キルナを過ぎ、鉄道は岩だらけの山岳フィヨルドの中腹を危なっかしげに縫いながら、ヨーロッパ最北端の駅ナルビクヘむかう。鉄鉱石の積出し港でもあるナルビクをめぐってナチス・ドイツと連合軍が沖合いで激しい争奪戦をくりひろげたところだ。
 この街で真夜中の太陽がみられるのは5月31日から7月14日までで、実に今日からだと分かったが、あいにく曇り空なのが悔やまれる。
この街で真夜中の太陽がみられるのは5月31日から7月14日までで、実に今日からだと分かったが、あいにく曇り空なのが悔やまれる。
同僚のホステラーが持参した御飯に梅干しと、日本茶で夕食をとる。
北極海の水は、港であるにもかかわらず澄み切っていて塩辛い。
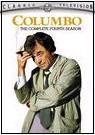 9時半にユースに泊まっている子供たちがワアッとテレビの前に集まったので、みていると白黒の「刑事コロンボ」がはじまった。
9時半にユースに泊まっている子供たちがワアッとテレビの前に集まったので、みていると白黒の「刑事コロンボ」がはじまった。
夜中2時半に起き、仲間とかたらいユースを抜け出して街に出かけ、白夜を撮る。太陽は山の端に隠れてみえず、その山を登るのは大儀なので断念する。